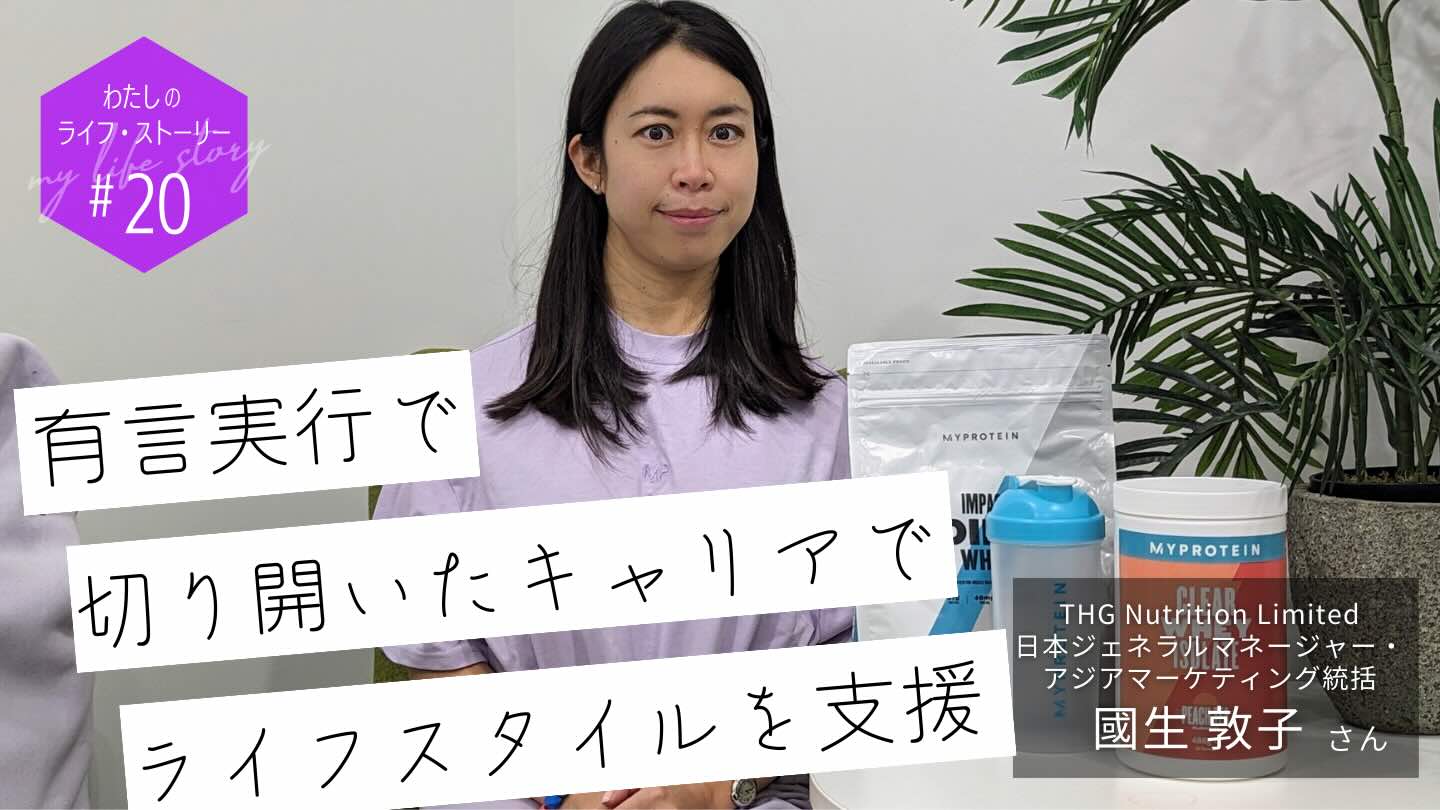2016年4月より、津田塾大学の学長に就任された高橋裕子(たかはし・ゆうこ)さん。大学院生活を終えて社会人になったのが32歳。その後、子育てと介護も経験しながら、研究者としてのキャリアを歩んできたそうです。
津田塾大学の助教授として母校に戻ってきたころは、子育てと介護の真っ最中だったとのこと。学長になるまでの長い道のりのなかで、何を考え、どう乗り越えてきたのか。
研究者になった理由からライフイベントの体験談、今後の展望についてお話をうかがいました。
女性が活躍する姿をみて決めた「大学院進学」の道

学生編集部:高橋学長はなぜ大学の教員になろうと思ったのでしょうか。
高橋学長(以下、敬称略。高橋):津田塾大学で大学生生活を送り、壇上で教鞭を執る先生たちをみて、自分自身ももしかしたら先生たちのようになれないかなと思ったのです。大学3年生くらいから大学院に進学しようかとぼんやりと考え始めましたが、当時はそれがどれほど長い道のりになるかについてはあまり考えていませんでした。
また、大学1〜2年生のときに大企業でアルバイトをした経験も、今後どのように生きていくかについて考えるきっかけになったと思います。会社で出会った女性は管理職に就いている方はほぼ皆無で、補助的な業務が中心でした。
でも津田塾大学に戻ってみると、女性の教授や管理職の職員が多くいらっしゃいます。普段見ていたその風景を、違った角度から捉えられるようになったのです。
学生編集部:当時、大学院進学する女性は少なかったのではないでしょうか。
高橋:そうですね。当時、私が所属していた10数人のゼミで1人でした。
私は1980年に大学院に進学し、筑波大学とカンザス大学で修士号を取り、89年にPh.D.を取得するまで合計で約9年間大学院生活を送ることになりました。結果として、他の人たちと比べて10年遅れて32歳で社会人になりました。皆と違うトラックを歩いていましたが、人と同じことをしなくてもいい、同じじゃなくてもいい、という思いをもたせてくれたのは津田塾大学の4年間だったと思います。大学院生の頃に津田梅子の書簡が発見されて、博士論文で津田梅子や女子大学の研究に取り組み始めました。このテーマが私のライフワークとなりました。
学生編集部:9年間の大学院生活はかなり長いと思うのですが、途中で揺らがなかったのでしょうか。また「結婚・出産」については当時どう思っていらっしゃいましたか?
高橋:修士課程を日本とアメリカ両方で合計4年間、学びました。博士課程を始める前の半年間は日本に滞在していて、青年海外協力隊の研修所で、短期間、英語を教えたりもしていたので、長くなったのですが、Ph.D.は帰国するまでに終わらせようと思っていました。「結婚・出産」を具体的に考える余裕はなかったかなぁ。
学生編集部:私の周りには、結婚も育児もしてそのまま働き続けたいという目標を持った学生が多いのですが。
高橋:私も、仕事をしながら、結婚もして出産もして…… というイメージはなんとなくあったかもしれませんね。
キャリア形成のロールモデルとなる女性に出会えた学生時代
学生編集部:大学時代は、どのくらい自分のキャリアについて考えていたのでしょうか。
高橋:私が大学生だったのは1970年代です。当時は、若い女性アナウンサーは政治のニュースは読ませてもらえず、番組のアシスタントか天気予報を担当するぐらい。そしてこれは今もそうですが、中高年の女性が積み重ねた知見を活かし発信するような場面はメディアでは多くはありませんでしたね。
当時大学生だった私は、男性は色々な経験を積み重ねて、評価されるのに対し、女性は外見などの身体的な魅力に焦点がおかれることに、違和感を覚えました。
津田塾大学の学生時代に出会った女性の先生方は、中高年になって評価される、輝けるものを持っているいぶし銀の女性のイメージとでも言えるでしょうか。その影響は大きかったと思います。
学生編集部:先生は、大学生の頃からずいぶんと長期的視点で女性の人生を見ていると思います。どうやったらそのような視点を持てるようになるのでしょうか。
高橋:実際に活躍している女性に日常的に触れることができたからです。ロールモデルにしたい女性の先生の授業は一番前の席に座って、どうやってここまで来たのか、どのように研究の道を切り拓いたのかなど、関心を持って聴いていました。
また、院生時代、津田塾大学の図書館でリサーチをしに帰国していた際に、津田塾大学の元学長であった藤田たき先生の講演会に行き、その後、ご自宅へインタビューに伺ったこともあります。当時、藤田先生は80代でいらしたでしょうか。様々な困難を乗り越え、力強く人生を切り拓き、生き抜く女性像が目の前に存在するということは、まさに津田塾大学の伝統の根幹だと感じました。
子育てに介護……ライフイベントが重なり、両立と向き合った30代後半
学生編集部:キャリア形成にとって育児が障害に感じられたことはありますか?
高橋:そういう風にネガティブに思ったことはないです。私は、1992年に結婚して、その1年後に男の子を出産しましたが、実は子どもが産まれる前に母が病気になっていました。母は子どもが1歳の誕生日を迎えたほぼ2週間後に亡くなりました。その年の夏、今度は父がガンであることが分かったんです。そして子どもの小学校の入学式があった週の日曜日、父も他界しました。そのとき、つまり子どもが0~6歳の間は、家、保育園、大学、病院、と4地点をぐるぐる回って育児と親の介護もしていました。
でも、仕事を辞めようとか長期にわたって休職しようと考えたことは1度もなかったです。親の容体が芳しくないなど、精神的に大変なとき、子どもが何よりも力を与えてくれる存在でした。朝、子どもを後ろに乗せて自転車で保育園に向かうとき、坂を上がろうとペダルを踏みこむタイミングに合わせて「おかーさん、がんばれ。おかーさん、がんばれ。」って声をかけてくれたことなど思い出します。子どもも、この自転車こぎのかけ声のことを覚えていると言います。
学生編集部:お子さんは当時のことを他に何か覚えていたりしますか?
高橋:子どもが4歳から8歳くらいのとき、『津田梅子の社会史』という本をまとめていました。とにかく子どもを寝かせないことには何もできないので、まず9時には一緒に寝て、3時頃に起きて書斎に向かうのですが、私が起きるとなぜか子どもも起きてきて…… それで、子どもを膝に乗せ、頭を肩に寄りかからせながらパソコンを打ったりしていたこともありました。その記憶も残っていると話してくれます。
学生編集部:研究者はなかなか育児がしにくいと聞いたことがあります。
高橋:私は35歳で親になりました。
ただ、母が病気になり、育児をし、父の介護をしながらさきほど述べた4地点を回っていた間は、研究が十分にはできませんでした。その当時、私は人生のそういう段階にあるんだと考えていましたね。思い返せば1980年代、私は色々な人からサポートを受けつつ自分中心の生活を送ることができた、と。大学院での生活を長くできたのは、両親が全面的にサポートをしてくれて、周りの人たちも支えてくれる環境があったからです。だから、自分のスケジュールで動けました。学生の時はそれに何の不思議もなかったけれど、1990年代にライフイベントが立て続けにあって、自分のスケジュールを自分で決められなくなった。
仕事とともに、子ども・両親・夫・夫の両親…… 様々な要素の中で自分のスケジュールを調整しなくてはならないわけです。80年代とは全く違う10年になったんです。論文を毎年書くようなことはできないけれど、それでもこの時期はこの時期で受け入れて、やらなくてはならないことを頑張ろうと思っていました。だから、研究できないからといってあまり悲観することもなく、ああ、向かい風が強い時期なのだと。だったら、その風とうまく付き合いながら、育児と介護を一生懸命やって、次の段階へ向かっていこうと、割と楽観しながら1990年代を過ごしていました。
だからこの時期、アメリカ研究者なのにアメリカにもなかなか行けなかったんですよ。1991年に行ったきり、次にアメリカに行ったのは2002年でした。2002年からようやくもう1度海外に出られるようになったんです。それまではずっと国内だった。だからといって、アメリカに行けなくて残念という気持ちもなかったですね。
学生編集部:2002年がターニングポイントだったと。
高橋:そうです。子どもが小学校に入り、両親の法事も一段落して、様々なライフイベントが落ち着いたのが2002年でした。
2002年は久しぶりのアメリカで、最初に6月のバークシャー女性史会議(コネティカット大学にて開催)に行って、7月には世界の女性学会議がマケレレ大学であってアフリカのウガンダに向かいました。その後8月には、同窓生が企画した津田梅子の足跡をたどる旅のヒストリカルガイドになってほしいというご依頼を受け、再びアメリカへ行き、帰ってきた翌日に今度はアフガニスタンに女子教育支援で行きました。
2003年から04年には、海外研修の期間をいただけたので、フルブライトの客員研究員としてスタンフォード大学で子どもと2人で暮らしました。子どもとともに海外の暮らしを経験できたのは本当に良かったですね。小学生だった子どもを通して得られた経験も多く、生活が豊かになりました。自分が積み重ねた研究の世界はもちろん私にとって重要ですが、もう1つの世界―子どもを育ててきた家族の世界も、自分を支えてくれる大切な部分だと考えています。
学生編集部:ライフイベントを経験して、女性が働くことについての考えが変わった部分はありますか。
高橋:私はきょうだいがいない分、周りの方々から様々なことを教わりました。私が出産した時はまだ育児休暇なんて取れなかったので、色々厳しかったんです。例えば、子どもが病気になったらどうするか、母乳保育のこと、出産の仕方…… などなど。
産育の比較研究をされている社会学の先生からは、一口に出産といっても、様々な形があって、産み方は自分で選ぶんだ、と教えてもらいましたし、子育て中の同僚からは色々な情報を教えていただきました。さらに、例えば、保育園のママ・パパ友のみなさんには、育児の面で大変お世話になりました。ママ友の中には、看護師さんや介護職の方などもいらして、父の訪問看護のことなども含めて助けていただきました。
お世話になっている人の子ども3人を連れて一緒にプールに行ったこともあります。楽しかったですね。そのような経験は、大学で働いているだけではできないですから。ライフイベントを通して学んだことは、そのようなネットワークができ、子どもも様々な人たちとの関わりの中で一緒に育ててもらえたことでしょうか。
キャリアアップに前のめりな果敢な女性を育てていきたい
 学生編集部:学長として、1人の女性として、今後どのような女性たちを育てていきたいでしょうか。
学生編集部:学長として、1人の女性として、今後どのような女性たちを育てていきたいでしょうか。
高橋:先日、津田塾大学の総合政策学部創設記念シンポジウムで、客員教授の村木厚子先生の基調講演を拝聴しました。村木先生からのメッセージがとても印象に残っています。村木先生は次のようにおっしゃいました。
1つは、新しい仕事をやる機会があったら、必ず引き受けなさいということです。
長くやり、得意な仕事のほかに、全く毛色の違う新しい仕事を引き受けることで間口が広がり、実力がつくからです。経験した仕事は足し算ではなく、掛け算で実力が蓄積されていくのです。
2つ目は、昇進のオファーがあったら受けなさいということです。
昇進というのは階段を上ることです。下の段にいて見えなかったことが、上の段に行くと、背が伸びたわけでもないのに見えるようになることです。下にいたら背伸びしたりジャンプしたりしないと見えないことが、階段を上ることによって見えるようになる。だから、下の段にいて「私はまだ見えないからできません」ではなくて、上がれば見えるようになるから上がりなさい、と言います。
村木厚子先生は厚生労働省の事務次官を務めた方ですが、女性がまだまだ数少ない官僚組織の中でご活躍されました。現在、日本のジェンダーギャップ指数は世界の144か国中111位であり、とりわけ政治・経済の分野に女性が十分に参画できていません。日本は世界と比べ、それほど差がついている社会です。つまり、様々な意思決定の場に参画する女性が増えていくことが重要なのです。ジェンダーギャップ指数の低い国に生きていると、高い国のイメージがなかなか沸きません。しかし、女性が仕組みを変える側に回り、仕組みを変える方法を習得していく。そのような展望を、学生たちに持ってもらいたいです。
フェイスブックのCOOであるシェリル・サンドバーグさんが書いた「LEAN IN」という本があります。LEAN INという言葉は、「前のめりに」という意味があります。本学の創立者である津田梅子は6歳の時に横浜を出て、初の国費女子留学生の一人として岩倉使節団に伴われてアメリカに向かって航海しました。サンフランシスコが見えてきた船の上で草履を脱ぎ、未知の世界に向かって前のめりになっている姿が描かれている屏風絵があります。この姿がまさに “LEAN IN”と言えます。未知の世界に眼光鋭く挑戦する意思を持って立ち向かうこの姿。この果敢な姿に、津田塾大学の源流にある建学の精神が見て取れます。
「女性だから」「ライフイベントがあるから」と考えがちな女性たちにとって、自分のやり遂げたいことを決して諦めない、勇気を与えてくれるロールモデルに出会うことの大切さを学びました。
プロフィール
高橋 裕子さん
津田塾大学学長
同大学英文学科卒業、筑波大学大学院(国際学修士)、米・カンザス大学大学院(M.A., Ph.D.)などを経て、1997年から同大学専任教員、2016年4月より現職。専門は、アメリカ社会史(家族・女性・教育)、ジェンダー論。著書に、『家族と教育』(明石書店、2011年)(共編著)、『女性と高等教育- 機会拡張と社会的相克』(昭和堂、2008 年)(分担執筆)、『津田梅子の社会史』(玉川大学出版部、2002 年)(単著)(アメリカ学会清水博賞)等。日本学術会議連携会員、アメリカ学会副会長。
文・インタビュー:若林里歩(学生編集部)
ライター