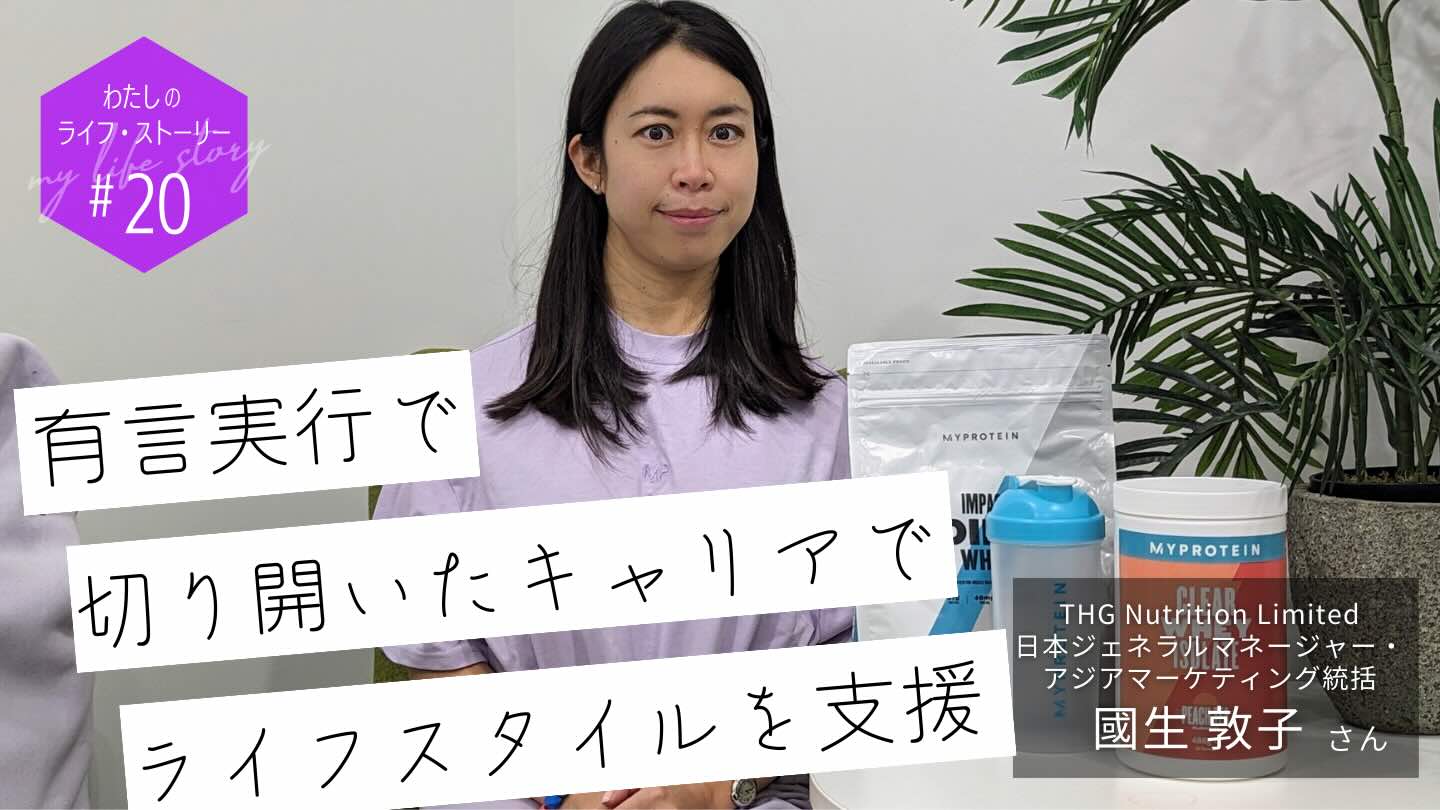地元愛を突きつめて見えてきた「うつろい」
ノリや流れに任せられるのも”必然”だから

岩手県一関市。世界遺産平泉を擁す歴史ある城下町です。その地で祭りを通じて地域と深く結びついている老舗染物屋の株式会社京屋染物店。社長の弟で専務の蜂谷淳平氏は、自社の事業だけでなく、一般社団法人世界遺産平泉・一関DMO理事や、伝統芸能である舞川鹿子躍の担い手として地域と関わり、活性の一助を担っています。特定の産業をベースとしない地域活性化に対し、個人・企業がどう関わっているのか、お話を伺いました。
家は地元のおじさんが集う集会所のよう
生き方の模索のため、家業へ

株式会社京屋染物店専務・蜂谷淳平氏 里山文化発信拠点「縁日」にて
——蜂谷さんの目には、家業はどのように映っていたのでしょうか?
染物にはいろいろありますが、うちは半纏といった祭り関係の染物がメインなので、地域の方々と密接な関係です。祭りが近い時期になると家に近所の方々が集まって話し合いという飲み会が行われていました。みなさん祭りというプロジェクトを楽しんでいて「染物屋が街をつくっているんだな」と感じていました。
——大学は東北芸術工科大学を選ばれたとのことですが、幼い頃からゆくゆくは家業へとの思いがおありだったのですか?
いえ、まったく(笑)。当時はプロのスノーボーダーになろうと思っていて、山に近かったので選びました。芸大なので絵で入学しましたし、在学中に藍染のTシャツを学内のイベントで販売したり、同じく藍染の卒業制作で優秀賞をいただいて展示会や海外販売をしたりはしていましたが、モノづくりがしたいという気概があった訳ではありませんでした。次男ですし(笑)。
卒業時にはプロへ進む気はなくなっていましたが、まだ具体的に他に何がしたいというものもありませんでした。現在社長を務める兄が既に家業に入っていて「仕事も地元も面白くしたい。一緒にやろう」と兄に誘われる形で入社したのですが、家業を担うというより、これからの生きる方向性を見つけるためという思いの方が強かったです。
父の余命宣告と震災で考えた“未来”
削ぎ落として残った“芯”

被災地から送られてきた法被
——そこから家業を生きる道と決められたのはきっかけがあるのですか?
2010年に父が他界したのですが、その半年前に余命宣告を受けまして。それまでは決して志高く家業に関わっていた訳ではありませんでしたが、その時初めて今後のことを兄とともに真剣に考えました。幸い、宣告を受けてからも父は元気でいてくれたので、さまざまなことを話し、学ぶことができました。父と一緒にした最後の仕事が鹿子躍の衣装制作です。
そして父が亡くなった翌年、東日本大震災がおき、世間は祭りどころではない状況になりました。しかし、祭りどころの状況ではないにも関わらず、津波でボロボロになった半纏が「どうにか修復できないか」と送られてきたのです。それに対し無償でお応えしたのですが、改めて「祭りとは何だろう」と考えるきっかけになりました。
そこで「祭りとはコミュニティを、絆を繋ぐこと。そこに染物屋は深く関わっていること。それが自分がやりたかったこと」という考えに至ったのです。
——決めてからの動きはどのようなものでしたか?
そこからは、まだまだ半人前だった技術を高めるために全国の染物屋さんで修行させていただきました。そして帰ってきてからは、工場の整備をはじめ、事業の整理もはじめました。
祭りに関わる人が減り、企業・行政も祭りに資金を回す余裕がなくなり、このままではジリ貧になることは見えていたので、改革は必須でした。人を採用しては辞め、新商品開発をしては鳴かず飛ばずなことも多かったですが、祭りを残すためにも、新しいことにチャレンジして両軸で回していくしかないと思いました。

右端が蜂谷さん。生まれた時から”祭り”が生活の中にあった
しかし、一番のチャレンジは「捨てる」ということでした。当時、染物以外でも祭りに関わるものであれば、仕入れをして小売業もしていたのですが、染めに比べて気持ちが乗っているものではありませんでした。そのような事業を畳むことにしたのです。
父が手作りした染め台など思い入れのあったものも、断腸の思いでしたが機械へと入れ替えたりもしました。モノを残すことが父の思いを守ることではないと思いましたし。
不要なものを削いできたからこそ「芯」となるものが見えた感じです。自分達はローカルで何をしていくか、何者なのか? と。それはやはり「祭り」が中心にあって、そこを支える存在でありたいと決めました。
勇気のいる決断でしたが、不要なことは知らず知らず脂肪のようについてくるので(笑)、今でも削ぎ落とすことは続けています。
“ノリ”で作ったDMO。愛あればこその勢い

DMO立ち上げメンバーと 左端が蜂谷さん
——家業に本腰を入れられるようになってから、続いて一般社団法人世界遺産平泉・一関DMOの理事や、東北初のオープンファクトリーの実行委員など、いくつかの地域団体・施設の立ち上げをされていますが、どのような経緯だったのでしょうか?
自分達の「芯」を見つけたことで「祭り」についてより深く考えるようになっていて。なぜ岩手は日本一郷土芸能が多く、鹿子躍に至ってはどうやって300年も続いているのだろう?とか。海も山も近く、運命共同体として自然を大事にしていることを文字などではなく体現しているのが踊りであり、人間側、自然(鹿)側を精神的に行き来するような繋がりが岩手の人の根幹にあるなと思いました。そこをきっちり伝えていくことが重要なんじゃないかなと。
——その伝え方がDMOだったと?
もともと地元にはうちのように商売をしている家が多く、今、私の同年代が後を継いでいて、子どもの頃、親世代の人たちが集っていたように、集まっては話したり飲んだりしています。そしてみんな地元が大好きなので、自然と街についての話になるんです。
一関は世界遺産があるにも関わらず、観光が弱く通過されてしまいがちなんですね。そこをなんとかしないといけないけど、行政に任せっきりだと面白くない、面白いことしよう!とある種ノリと勢いでDMOをつくった感じです。でも、その勢いがなければ作れなかったとも思います。
ノリで始めましたが、きちんと組織だてて活動を行ってきたため、結果も順調に出ていて、ふるさと納税が300万円から15億円を超えるまで増えました。ここで財源を得て、まちづくりをますます進めていきます。
具体的には、平泉をはじめ、一関含め奥州3エリアの自然・里山文化の魅力を知ってもらう体験ツアーなどを行ったり、拠点をつくったりして発信を続けています。
家業の方でも、自分達の「芯」を他社がキャッチアップしてくれて、例えばSnowPeakとの「ローカルウエア」コラボなどに繋がっています。
自然と人の境界とは?狩猟や踊りの体験が見せたもの

300年、民衆によって伝承されてきた舞川鹿子躍。岩手県無形民俗文化財
——里山文化を伝えるにあたり、狩猟や鹿子躍を始められたのでしょうか?
鹿子躍は小さい頃から見てきましたし、大人になってから見てもそのトランス感というか、アートとしてかっこいいなと。やってみたいなと思い、踊り手として参加し始めました。「継承しなければ!」との気負いではなく、「自分のアイデンティティとして体感したい」と。総重量15kgくらいの衣装をつけて踊るので、かなりハードな踊りです。踊っているとだんだん自分が人間なのかシシなのか境目がわからなくなってきて、自然と繋がり合っていることを強く感じられるのです。
狩猟に関しては、岩手県では年間25,000頭ほどの鹿が害獣として駆除されています。これをジビエとして活用することも考えています。そこに命のやりとりがあることを頭ではわかっていても、実際に経験してみないと見えないものもあるのかなと、自分でも狩猟を始めました。
1年目は「かわいそう」という思いの内うちに「狩猟の面白み」を感じている自分に罪悪感のようなものもあったのですが、2年目で鹿を実際に仕留められるようになってきて、捌いている時に眼や筋肉が動く様子などを見るにつけ「死とはなんだろう?」と考えるようになりました。そして、“死”とは医療上の定義であって、人の営みも含め、全ては「うつろい」なんだなと思い至るようになって。
狩猟と鹿子躍の体験で、両者の視点でその中に自分も入り込むことで、モノの見方が変わったというか、もともとあった感性が呼び覚まされたような感じもしています。
この「うつろい」を非常に科学的に捉えてずっと継承してきているのが、狩猟と鹿子躍であり、ここの里山文化なんです。サスティナブルという言葉がない時から、おそらく日本一自然という運命共同体を大事に思いその循環を体現している場だと思います。
“官”ありきではなく、まずは自らが立つことから
地域活性は始まる

祭り衣装・郷土芸能衣装の技術を普段着に落とし込んだオリジナルブランド「en*nichi 」。東北地方の伝統的な野良着である猿袴(さっぱかま)の意匠とパターンをもとに製作した普段着「SAPPAKAMA」でグッドデザイン賞を受賞。
——その体現していることを共有することで、人を惹きつける。確かに他とは違った地域の魅せ方のような気がします。お祭りを通じて“公”とは繋がりが強いと思いますが、“官”とはどのように関わるのが良いのでしょう?
昔は行政も祭りに対して財源を割いていましたが、近年はその余裕はなくなってきています。祭りがコミュニティ、ひいては街をつくっていっている一関では特に、“官”が主導して何かを起こしてくれることを期待するのではなく、まず“民”である我々事業者・企業、個人が自立して活動できる状況を作る必要があると思います。その上で、官(行政)と連携・協力を求めるべきなのかなと。今、うちの事業が観光の拠点や発信の中心となっているので、役所の方々に視察にきていただいたりしています。うちにしかできないことでリーダーシップを発揮しながら、今後、より関係を深めていけたらと思っています。
自社のことだけを考えるのではなく、地域みんなでよくなっていきたいと思っているので、その姿勢が市や県のバックアップを受けやすいのかもしれません。
でも、一番は行政の中ですごく話のわかるキーパーソンを探すことだと思います!
自然と運命共同体であり、人の生活も自然界の「うつろい」の流れの一つ。とっても腹おちのするお話でした。モノの理だからこそ、誰でも感じ入ることがあって、それは日本人でなくても同じなのでは?と思いました。それをインバウンドも含めた”観光資源”とするところに、蜂谷さんの手腕と地元への愛を感じるお話でした。
プロフィール
蜂谷淳平さん
株式会社京屋染物店 専務取締役
蜂谷淳平(はちや・じゅんぺい)
株式会社京屋染物店 専務取締役。東北芸術工科大学卒業後、家業である京屋染物店に入社。2017年に、一般社団法人 世界遺産平泉・一関DMO 立ち上げ理事に就任。2018年、東北初のオープンファクトリー『五感市』を立ち上げ実行委員長を務める。2019年、SnowPeakとの共同事業『LOCAL WEAR』では、土地の物語を着る服作りとして、年2回のツーリズム事業も並行してスタート。同年、自社ブランド『en・nichi』がスタートし、東北の衣服と人の暮らしを紐解きながら、現代の生活に寄り添う服作りを始める。2022年、岩手で害獣駆除された鹿の皮を使ったプロダクト『山ノ頂』をリリース。2023年、ローカルの文化の発信拠点として、岩手県一関市の里山に新拠点『縁日』を構える。舞川鹿子躍と狩猟を実践し、人と自然の共生のあり方を探究する日々を過ごす。
ライター